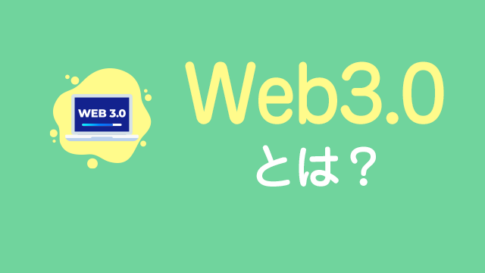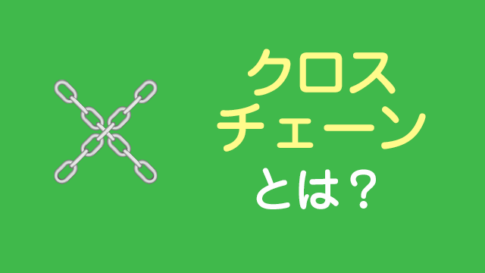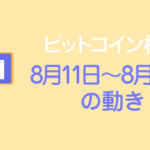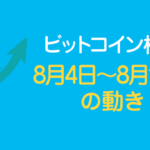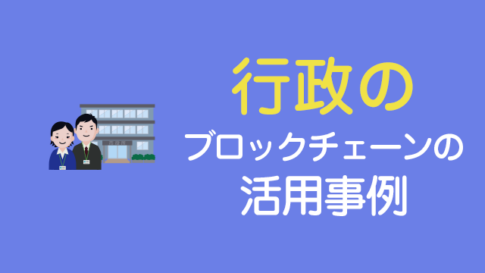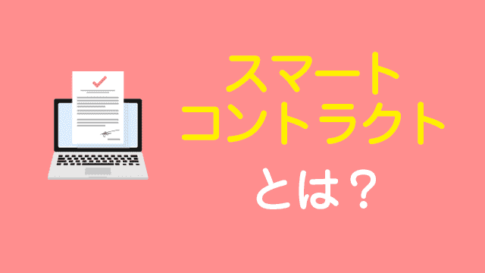暗号資産BIO Protocol(BIO)の特徴
一般の企業や団体、個人が資金を調達するのは昔は容易いことではありませんでした。
しかし、最近は、しっかりとした目的や目標があればクラウドファンディングで資金調達出来るようになってきています。
これを暗号資産で行うプロジェクトが「BIO Protocol(BIO)」です。
今回は、この「BIO Protocol(BIO)」について解説していきたいと思います。
BIO Protocol(BIO)のアウトライン
| 発行上限 | 約33億枚 |
| 特徴 | DeSci(分散型科学)プラットフォーム |
| 発行開始 | 2024年1月 |
BIO Protocol(BIO)は、ブロックチェーンの技術とバイオテクノロジーを結びつける、DeSci(分散型科学)と呼ばれる新しい分野のプロトコルです。
科学研究の資金調達・管理・研究成果の共有を、より透明で誰もがアクセスしやすい形に変えることを目指しています。
バイオテクノロジーに特化したプロジェクトや、IP(知的財産)への出資や開発等を進める他に、Web3.0の技術や概念を学習できるプロダクトの提供なども行っています。
BIO Protocol(BIO)の特徴
BIO Protocol(BIO)の特徴を挙げていきます。
分散型の研究資金調達
従来の研究では、少数の大規模な資金提供者(政府機関・財団・大企業等)に資金調達を依存していました。
BIO Protocol(BIO)では、研究者は、自身の研究プロジェクトの概要をプラットフォーム上で公開したり、プロジェクトに関心を持つ個人や団体が、BIOトークンを使ってプロジェクトに直接資金を提供します。
これによって誰でも研究のスポンサーになることが可能になっています。
知的財産のトークン化
研究の成果として得られた知的財産(IP)を、NFTのようなデジタル資産として表現しています。
創薬や遺伝子研究から生まれた新しい技術やデータは、トークンとして細かく分割され、資金を提供したコミュニティメンバーに分配されます。
トークン化することで、IPを自由に売買できるようになり、研究者も投資家もより迅速に利益を享受できるようになります。
BIO Protocol(BIO)の今後
BIO Protocol(BIO)の将来性について挙げておきたいと思います。
DeSci(分散型科学)市場の成長
DeSciは、従来の閉鎖的な科学研究モデルをブロックチェーンによって変革しようとする新しい分野です。
BIO Protocol(BIO)では、この成長市場の初期段階に位置しており、バイオテクノロジーという特定の分野に焦点を当てることで、ニッチなマーケットで主導的な地位を築く可能性があります。
クロスチェーン展開
BIO(Bio Protocol)ではクロスチェーン展開を進めており、今後さらにユーザーの数が増える可能性があります。
初めはイーサリアムチェーン上のみで展開していましたが、ソラナチェーン、Baseでの展開となってきています。
今後もこのようなクロスチェーン化の加速により、より多くのユーザーがBIO(Bio Protocol)を認知し、ユーザーの利便性が高まると思われます。